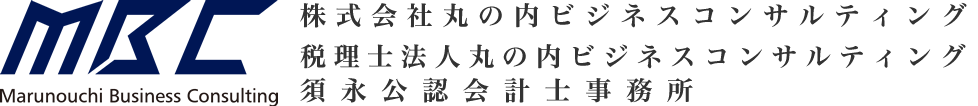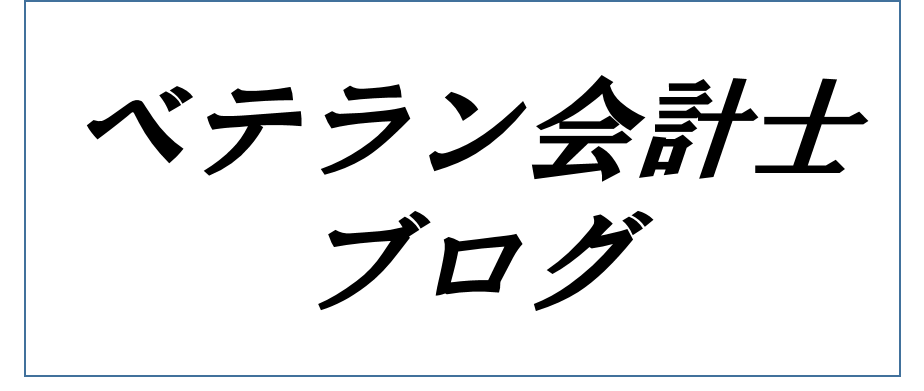でんた丸ブログ
地方公共団体間での税源の偏在
我が国では、地方公共団体間で税源が偏在しているため、住民1人当たりの税収額の格差が極めて大きい点が問題となっています。特に地方税の計40数兆円の約2割を占める「地方法人2税」と呼ばれる法人住民税(法人税割)と法人事業税の税収が、東京都などの大都市圏に偏在しています。このような格差を是正するために、国税(国が賦課・徴収する租税)を地方公共団体に交付ないし譲与する地方交付税と地方譲与税がありますが、このような名称の税目があるわけではありません。今回は具体例でこの点をみていきます。(なお、次回からはリース会計基準の改正についてみていきます。)
1.地方法人税
地方法人税法は平成26年に公布・施行され、地方税である法人住民税(法人税割)の一部を地方交付税の原資にする趣旨で、地方法人税が創設されました。地方交付税法により、国税である地方法人税の全額が一定の基準に基づき、地方公共団体に配分・交付されます。
※法人税確定申告書と地方法人税確定申告書を1つにした様式を使用することで、両申告書の提出を同時に行えるようになっています。
2.特別法人事業税
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律は平成31年(令和1年)に公布・施行され、地方税である法人事業税(所得割・収入割)の一部(法人事業税の約3割)を分離する形で、特別法人事業税(国税)と特別法人事業譲与税が創設されました。地方譲与税の1種である特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の全額を都道府県に譲与するものです。
※特別法人事業税は、法人事業税と同じ申告書・納付書により、法人事業税と併せて都道府県に申告納付することになり、いずれか一方のみを納付するということはできません。そして、法人事業税と併せて納付された特別法人事業税は、都道府県から国に対して払い込まれ、特別法人事業譲与税として各都道府県に再配分(譲与)されます。
このような再配分は、地方への税源移譲ではなく、国主導の財源調整という集権的手法(いわゆる「ばらまき」)であり、地方の国依存を深めているという批判があります。現に、自立して財政運営できる自治体の数(地方交付税を受け取らない不交付団体の数)は、リーマンショックを機に急減して以降、増加傾向にあるものの極めて緩やかなものにとどまり、リーマンショック前の140超の半分程度で足踏み状態にあります。
相続税の課税対象になる死亡退職金
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といい、現物で支給された場合も含まれます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて(いわゆる「みなし相続財産」)、相続税の課税対象となります(相続税法3条1項2号)。
このように相続税の課税価格計算の基礎に算入される退職金は、退職所得(所得税法30条1項)に該当しないため所得税は課税されず(所得税基本通達9-17)、「退職所得の源泉徴収票」(注)ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を提出することとなります(相続税法59条1項2号)。
なお、死亡した者の退職金であっても、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、相続税の課税価格計算の基礎に算入されないので、遺族の一時所得として所得税の課税対象になりますが(所得税基本通達34-2)、この場合には、「退職手当等受給者別支払調書」等の法定調書の提出を要しません。
(注)所得税法226条2項により、「退職所得の源泉徴収票」を提出するのは、退職所得に該当する退職手当等とされています。
物納
物納とは、金銭(納税適格証券及び印紙を含む。)で納付する代わりに、金銭以外の財産で納付する方法のことをいいます。国税通則法34条3項では、「物納の許可があった国税は、…国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。」と定められているところ、現在では相続税においてのみ物納が認められています(相続税法41条以下)。
1. 物納に充てることのできる財産(相続税法41条2項)
まず、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産である必要があるため、例えば、相続開始前から納税義務者が自ら所有する不動産を物納に充てることはできません。
※延納の制度(相続税法38条以下)が別途用意されており、納税義務者により頻繁に利用されています。
また、相続税法施行令18条に規定される管理処分不適格財産も物納に充てることができません。物納申請財産は、国に帰属させて、これを使用収益することを目的とするものではなく、当該物納申請財産の金銭的価値に着目して、国がこれを最終的に処分して国家の収入に充てることにより、金銭の納付に代わる経済的利益を得ることを目的とするものだからです。
2. 物納財産の収納価額(相続税法43条1項)
原則として、課税価格計算の基礎となった当該財産の価額となります。
3. 物納財産により納付があったものとされる時(相続税法43条2項)
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があったものとされます。
共同相続人の連帯納付義務(法改正の変遷の一例として)
共同相続人は、自らが負担すべき固有の相続税の納税義務について確定すると、法律上当然に、連帯納付義務も確定し特別の責任を負うことになります(相続税法34条1項)。この相続税法34条という条文は、今では1項に本文と但書があり、しかも8項まで規定が整備されていますが、平成23年(2011年)6月の改正までは1項に但書はなく、また5項から8項までの規定もありませんでした。どのような問題意識から条文が見直されるのかをみるため、今回は相続税法34条を取り上げます。
1.平成23年6月改正に至るまでの問題意識
共同相続人として当然に負担することになる連帯納付義務につき、連帯納付義務者に対して納税の告知がないまま徴税がなされ、当該連帯納付義務者からすると不意打ちであり困惑してしまうという問題が生じていました(確定した租税に係る徴収手続上の問題点)。
2.平成23年6月改正
上記1.の問題に対処し、連帯納付義務者のために適正手続を保障する観点から、平成23年6月に相続税法が改正され、34条に5項から8項までの規定が創設されました。
3.平成24年3月改正
相続開始から長期間が経過したにもかかわらず、突然、連帯納付義務者に対して連帯納付義務の追及がなされると、当該連帯納付義務者の法的安定性が著しく害されます。そこで、平成24年3月改正で、34条1項に但書が新たに加わり、連帯納付義務者の連帯納付義務が解除される3つの場合に係る規定(1号ないし3号)が創設されました。
なお、1号から3号の内容を簡潔にまとめると次のようになります。
1号:本来の納税義務者の相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)から5年が経 過する日までに、税務署長から連帯納付義務者に対し納付通知書による通知がなかった場合
2号:本来の納税義務者が「延納の許可」を受けた場合
3号:本来の納税義務者に「納税の猶予」がなされた場合
財産評価基本通達6項の適用を巡る判決(その2)
前回は、不動産の相続税評価に係る最高裁令和4年4月19日判決をみました。財産評価基本通達(以下「評基通」という。)6項はその適用対象を限定していないところ、非上場株式の相続税評価に関して評基通6項の適用の可否が争われた判決(東京地裁判決令和6年1月18日、東京高裁判決令和6年8月28日のいずれにおいても、国は敗訴し、上告がなされなかったため、国の敗訴が確定しました。)について、前回の判決の事案と比較する形でみてみます。
【最高裁令和4年4月19日判決の事案】
・被相続人は平成24年6月17日に94歳で死亡した。
・同人は、平成21年1月30日付けで、信託銀行から6億3000万円を借り入れた上、同日付けで甲不動産を代金8億3700万円で購入した。
・同人は、平成21年12月21日付けで共同相続人らのうちの1名から4700万円を借り入れ、同月25日付けで信託銀行から3億7800万円を借り入れた上、同日付けで乙不動産を代金5億5000万円で購入した。
⇩
♦最高裁判決
被相続人及び共同相続人らは、近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において、上記購入・借入れが相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて企画して実行した。
甲・乙不動産の価額について評基通の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と共同相続人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきである。
【今回の判決の事案】
・被相続人が代取の会社(X社)の株式に関して、次のような経緯があった。
①平成26年5月29日、被相続人はX社株式をY社に対し譲渡する基本合意を締結した(譲渡予定価格:1株約10万5千円)。
②被相続人は同年6月11日に死亡した。
③同年7月8日、遺産分割でX社株式を取得した相続人らは、被相続人の妻に全てのX社株式を譲渡した(譲渡価格:1株約10万5千円)。
④同年7月14日、被相続人の妻は、Y社に対しX社の全株式を1株約10万5千円で譲渡した。
⑤平成27年2月27日に、相続人らは評基通180項に基づき類似業種比準価額(1株約8千円)で相続したX社株式を評価し、相続税の申告をしたところ、国は評基通6項を適用し1株約8万円で評価したため、評基通6項の適用の可否が争われました。
⇩
♦東京高裁判決
上記①の基本合意は、被相続人の生存中に売買契約が成立した場合、代金債権に転化し、又は代金が支払われることによって、相続税の負担を増大させる可能性を有するものであり、相続税の負担を減じ、又は免れさせるという効果は存しない。
従って、他の納税者との関係で不公平であると判断する余地はない。
結局、今回の判例の事案では、最高裁令和4年4月19日判決の事案におけるような、評基通の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるということはできず、評基通の定める方法による画一的な評価額と異なる価額とすることについて合理的な理由があるとはいえない、とされました。
このように国が評基通6項を合理的な理由もないのに濫用し適用すると、租税法の一般原則としての平等原則に違反し違法となります。